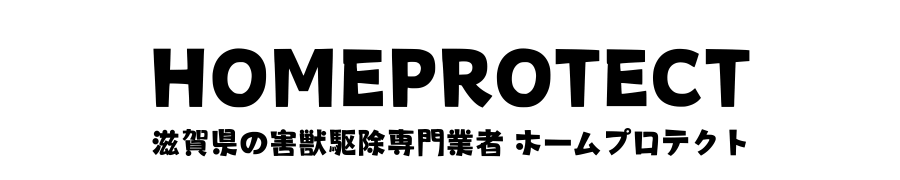日本に生息するコウモリは、実は害獣とされることもありますが、多くは害虫を捕食する益獣としても知られています。ただし、建物への侵入や糞尿による汚染、健康被害などから、特に都市部では問題となることがあります。ここでは、害獣駆除の専門家の視点から、日本にいるコウモリの種類とその特性について解説します。
1. アブラコウモリ (Japanese Pipistrelle)
- 学名:Pipistrellus abramus
- 特徴:日本で最も一般的に見られるコウモリです。体長は約4~5cm、翼を広げると20cmほどで、体重は5g前後と非常に小型です。
- 生息環境:都市部から農村部まで広範囲に分布し、建物の隙間や屋根裏に巣を作ることが多いです。特に住宅の屋根や壁の小さな隙間から侵入しやすいため、害獣として扱われることが多くあります。
- 害獣としての問題:
- 糞尿による汚染:巣を作る際に、大量の糞尿を放置し、これが建物を汚染したり、悪臭の原因になります。
- 寄生虫の媒介:コウモリに寄生するダニやノミが、人間に移動して健康被害を引き起こすリスクがあります。
- 病原菌:コウモリは狂犬病やヒストプラズマ症(糞に含まれる真菌による感染症)などの病原菌を媒介する可能性があり、注意が必要です。
2. ホンドコテングコウモリ (Greater Horseshoe Bat)
- 学名:Rhinolophus ferrumequinum nippon
- 特徴:テングコウモリ科に属する中型のコウモリで、体長は約7~9cm、翼幅は35~40cmほどです。顔の中央にある「鼻葉」と呼ばれる特徴的な突起が名前の由来です。
- 生息環境:森林や洞窟、さらには廃屋や古い建物の屋根裏に生息しています。比較的山間部に多いですが、都市近郊にも現れることがあります。
- 害獣としての問題:
- 建物への侵入:ホンドコテングコウモリも建物内に巣を作ることがあり、特に古い建物の屋根裏や倉庫などに侵入します。
- 糞の堆積:洞窟などでは糞が大量に蓄積し、悪臭や害虫の発生を引き起こすことがあります。
3. オヒキコウモリ (Asian Particolored Bat)
- 学名:Vespertilio sinensis
- 特徴:体長6~7cm、翼幅は約25cm。背中が黒褐色で、腹部は白っぽい二色の毛色を持つため、別名「二色コウモリ」とも呼ばれます。夜行性で、夕暮れ時や夜間に活発に活動します。
- 生息環境:森林地帯や川沿いに多く見られますが、都市部や農村部でも観察されます。屋根裏や倉庫に侵入することがあります。
- 害獣としての問題:
- 巣作りの被害:建物の隙間や天井裏に巣を作り、糞尿や鳴き声による被害が発生します。
- 衛生リスク:アブラコウモリ同様、寄生虫や病原菌を媒介するリスクがあります。
4. キクガシラコウモリ (Lesser Short-nosed Fruit Bat)
- 学名:Cynopterus sphinx
- 特徴:体長は約9cmで、翼幅は30cmほどの中型のコウモリです。名前の通り、キクの花のような特徴的な鼻を持っています。主に果実を食べる果実食性のコウモリです。
- 生息環境:日本では沖縄や南西諸島に生息しており、熱帯の森林や果樹園で見られます。都市部にはあまり出現しませんが、果樹園での被害が報告されています。
- 害獣としての問題:
- 農作物への被害:果物を主に食べるため、果樹園での被害が大きいです。特にマンゴーやパパイヤなど、栽培される果実に被害をもたらします。
5. ヤマコウモリ (Mountain Noctule Bat)
- 学名:Nyctalus aviator
- 特徴:体長は約8~9cm、翼幅は40cm以上の大型コウモリです。日本では北海道から九州まで分布しています。夜行性で、日中は洞窟や木の穴に隠れていることが多いです。
- 生息環境:森林や山間部に多く生息していますが、都市部近くにも出現します。建物への侵入は少ないものの、農村部では被害が報告されています。
- 害獣としての問題:
- 農作物被害:主に昆虫を捕食しますが、農村部では果実や作物への影響があるとされます。
- 騒音と糞尿被害:巣作りをする際には糞尿の問題や、群れで生活するための騒音が問題となることがあります。
コウモリ駆除のポイント
- 侵入経路の特定と封鎖:コウモリは建物の非常に小さな隙間からでも侵入できます。まずは侵入経路を特定し、封鎖することが重要です。
- 捕獲と駆除の適法性:日本では多くのコウモリが鳥獣保護法によって守られており、許可なく駆除することは禁じられています。専門業者による適切な対応が求められます。
- 衛生管理:駆除後には、糞尿や寄生虫の除去を徹底する必要があります。特にダニやノミが残ると、人間への二次被害が発生する可能性があります。
まとめ
日本に生息するコウモリには、害獣として問題を引き起こす種類がいくつかあります。糞尿による汚染、建物への侵入、健康被害などが主な懸念点です。駆除には法的な規制も伴うため、プロフェッショナルな対応が必要です。コウモリの生態を理解し、適切な防除策を講じることが重要です。